森山's Honey Bucket 22
春合宿の遠足で歩いた海岸沿いの道。
天候にも恵まれ、改めて島の風景に心を動かされた。
波静かな入り江、内海湾のおだやかさ。
高くそびえる星ヶ城・美しの原の両山の雄大さ。
山を深く刻み込む寒霞渓の荒々しさ。
小さな漁村の屋根を照らす陽の光のやさしさ。
青く高い空。自由な感じの雲。
なんともいえぬ春の香り、潮の香り。
それらの背景とみごとにマッチする子どもたちの笑顔。
そして歓声。
素敵なところ
すてきな時間
いつの日か、
スケッチブックやカメラを手に
ゆっくり、のんびり、島をまわることができたらいいのになあ…
てなわけで、久しぶりに個展?開かせていただきます。
(遠足の風景とはひとつも関係ありませんが…)
題名は上から
漁村の風景 古都の道 森山商会 冬の寺 当麻寺 塔遠望
PR
火曜担当なのですが、曜日を間違えていました。
申し訳ありません。
普段、どうしても、生徒や、自然を撮影することが多く、
教える側は、自分はもちろん、他のスタッフの写真を撮ることは
ほとんどありません。
というのも、他の先生が授業中は、当然、僕も授業中で、
そして、自分で、自分を撮る事ができないからなんですよね。

今回、学園の広報用に、いくつかの実験で、先生方の撮影をする機会があったのですが、
普段、他の先生の授業を見る機会が無いので、大変刺激的でした。
授業は、やはり、ライブ感、
顔の表情、身振り手振り、それらすべてが大切だと、
写真を撮りながら実感。
写真は、森山先生がマジシャンモードで、何かが憑依したかのように
声高らかに歌うシーンと、
みなさん、おなじみのアルコール燃焼実験の様子です。
そりゃ~、多感な時期に、こんな授業を日々、受けると、
他の先生の授業では物足りなくなるはずです(W

申し訳ありません。
普段、どうしても、生徒や、自然を撮影することが多く、
教える側は、自分はもちろん、他のスタッフの写真を撮ることは
ほとんどありません。
というのも、他の先生が授業中は、当然、僕も授業中で、
そして、自分で、自分を撮る事ができないからなんですよね。
今回、学園の広報用に、いくつかの実験で、先生方の撮影をする機会があったのですが、
普段、他の先生の授業を見る機会が無いので、大変刺激的でした。
授業は、やはり、ライブ感、
顔の表情、身振り手振り、それらすべてが大切だと、
写真を撮りながら実感。
写真は、森山先生がマジシャンモードで、何かが憑依したかのように
声高らかに歌うシーンと、
みなさん、おなじみのアルコール燃焼実験の様子です。
そりゃ~、多感な時期に、こんな授業を日々、受けると、
他の先生の授業では物足りなくなるはずです(W
こんにちは。林です。
先日(29日)、春合宿から帰ってきました。帰り道、晴れているのに雨?と思いきや、雪が降ってきました。どお
りで寒いはずです。なごり雪だなあと思いながら、車で走っておりました。帰宅後、ウェブで「なごり雪」を検索し
たら、なつかしい伊勢正三さんの歌に行き着きました。そういえば、高校時代に聞いていたなあと思い出しまし
た。かぐや姫は一世代前で、我々の世代は風からソロ活動あたりの頃だったと思います。(かぐや姫も風もグ
ループ名だよ。)風の歌では、「海風」が好きでした。歌というよりイントロが好きで今でもギターを弾く機会があ
れば弾いてしまいます。他に「そんな暮らしの中で」とか「ささやかなこの人生」とかyoutubeで聞いているとCD
でいい音で聞きたいなあと思いました。CDあったかなあ?探してみようっと。
先日(29日)、春合宿から帰ってきました。帰り道、晴れているのに雨?と思いきや、雪が降ってきました。どお
りで寒いはずです。なごり雪だなあと思いながら、車で走っておりました。帰宅後、ウェブで「なごり雪」を検索し
たら、なつかしい伊勢正三さんの歌に行き着きました。そういえば、高校時代に聞いていたなあと思い出しまし
た。かぐや姫は一世代前で、我々の世代は風からソロ活動あたりの頃だったと思います。(かぐや姫も風もグ
ループ名だよ。)風の歌では、「海風」が好きでした。歌というよりイントロが好きで今でもギターを弾く機会があ
れば弾いてしまいます。他に「そんな暮らしの中で」とか「ささやかなこの人生」とかyoutubeで聞いているとCD
でいい音で聞きたいなあと思いました。CDあったかなあ?探してみようっと。
● 春期合宿
小5から中3そして卒業記念旅行の子どもたちを連れての春期合宿が本日終了。
在学生
小56本科生はパズルを中心とした考える算数。
小56特錬生は「割合」の単元を集中学習。
中1から中3までは英語の徹底演習。
家にいては到底考えられないほどの勉強量だが、多くの先生の励ましや,
共にがんばる友達の存在もあり、懸命に課題に取り組んだ。
共にがんばる友達の存在もあり、懸命に課題に取り組んだ。
学習の合間には、「二十四の瞳」を映画化した時のロケ地跡である映画村を見学する。
片道5キロの道のりを、素敵な海の風景を眺めながら歩く。
片道5キロの道のりを、素敵な海の風景を眺めながら歩く。
卒業旅行生
自分たちで計画を立てて、自由に行動する。
受験を乗り越えた後の解放感に満ち溢れている。
四国に渡ってうどんを食べたり、一日中、星くずの村の運動場でサッカーや野球をしたり、
港に行って釣りをしたりと、自分たちのやりたいことに挑戦する。
この合宿が終われば新たな生活が待っている。
「星くずの村」に来ることは当分ない。そんな思いも働くのだろう、
若い助手の先生たちの手助けを受け、寝る時間も惜しんでやりたいことをこなしていく。
港に行って釣りをしたりと、自分たちのやりたいことに挑戦する。
この合宿が終われば新たな生活が待っている。
「星くずの村」に来ることは当分ない。そんな思いも働くのだろう、
若い助手の先生たちの手助けを受け、寝る時間も惜しんでやりたいことをこなしていく。
子どもたちはさまざまな体験を通して、大いなる刺激を受け成長する。
「星くずの村」での体験には、短期間のうちに子どもたちを大きく変えていく要素が一杯詰まっている。
次は夏合宿。どのような体験を子どもたちにさせていくか。こちらもわくわくしながら考えたいと思う。
今日はちょっとお疲れです。早く寝るとしよう。
今日はちょっとお疲れです。早く寝るとしよう。
ではまた。
わくわくの土曜日担当、池畑ことあっくんです☆
本日も僕のヒトリゴトにお付き合いください♪
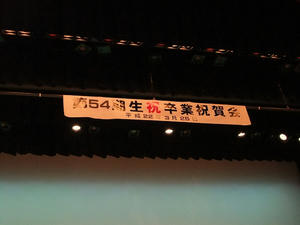
ついに54期生の卒業祝賀会が終わってしましましたね。
終わってみれば本当にあっという間の時間。
今年も笑いあり、涙あり、感動ありの本当に本当に素敵な時間でした。
1年のうちで藤原学園で働いていることに最も喜びを感じる日といっても過言ではありません。
とはいえ、同時にたくさんの「お別れ」をしなければいけない日でもあり、寂しく思う気持ちもいっぱい。
卒業生の中にも泣きながら「卒業したくない」と言ってくれる子がいました。
思わずもらい泣きをしながら、その短い学園に対する最高の褒め言葉を聞いていました。
僕も以前は、
「ホント卒業なんてなければなぁ…」
なんて思っていたこともあります。
でも何度も学園の祝賀会を経たことで、今はちょっと違っています。
「こんなにも感動できる日を迎えることができるのは終りがあるからこそなのでは」と。
「いつかは終わりの日が来る限られた時間であることを知っているからこそ大切に生きてきた日々があり、その積み重ねがこの感動を生みだしている源泉なのでは」と。
始まったものはいつか必ず終わりを迎える。
これは自然の摂理です。
モノはいつか壊れてしまう日がきます。
入学した学校をやがて卒業する日がきて、就いた仕事もいつかは退職する日を迎えます。
この世に生をうけた僕たちもやがてはこの世界に別れを告げる日がやってきます。
ならばいつか迎える様々な最後の日には、自分は大いに満足し、周りからは涙を流してもらえるようなそんな生き方ができれば素敵ですよね。
人間は生まれてくるときに苦しくて大泣きするが、周りの人たちは新しい命を大喜びで迎える。
正しい死に方とはその逆で、本人は満ち足りた心で死ぬが、周りの人はその人を惜しんで大泣きする。
『イーグルに訊け インディアンに学ぶ人生哲学』(天外伺朗 /衛藤信之著)より引用
本日も僕のヒトリゴトにお付き合いください♪
ついに54期生の卒業祝賀会が終わってしましましたね。
終わってみれば本当にあっという間の時間。
今年も笑いあり、涙あり、感動ありの本当に本当に素敵な時間でした。
1年のうちで藤原学園で働いていることに最も喜びを感じる日といっても過言ではありません。
とはいえ、同時にたくさんの「お別れ」をしなければいけない日でもあり、寂しく思う気持ちもいっぱい。
卒業生の中にも泣きながら「卒業したくない」と言ってくれる子がいました。
思わずもらい泣きをしながら、その短い学園に対する最高の褒め言葉を聞いていました。
僕も以前は、
「ホント卒業なんてなければなぁ…」
なんて思っていたこともあります。
でも何度も学園の祝賀会を経たことで、今はちょっと違っています。
「こんなにも感動できる日を迎えることができるのは終りがあるからこそなのでは」と。
「いつかは終わりの日が来る限られた時間であることを知っているからこそ大切に生きてきた日々があり、その積み重ねがこの感動を生みだしている源泉なのでは」と。
始まったものはいつか必ず終わりを迎える。
これは自然の摂理です。
モノはいつか壊れてしまう日がきます。
入学した学校をやがて卒業する日がきて、就いた仕事もいつかは退職する日を迎えます。
この世に生をうけた僕たちもやがてはこの世界に別れを告げる日がやってきます。
ならばいつか迎える様々な最後の日には、自分は大いに満足し、周りからは涙を流してもらえるようなそんな生き方ができれば素敵ですよね。
人間は生まれてくるときに苦しくて大泣きするが、周りの人たちは新しい命を大喜びで迎える。
正しい死に方とはその逆で、本人は満ち足りた心で死ぬが、周りの人はその人を惜しんで大泣きする。
『イーグルに訊け インディアンに学ぶ人生哲学』(天外伺朗 /衛藤信之著)より引用

